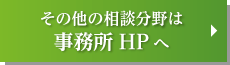特別受益と寄与分
「特別受益」と「寄与分」に関する制度概要
相続人が遺産分割の結果取得することになる具体的な相続分額は,通常,相続開始時に存在した相続財産の総額に法定相続分に応じて算定されます。しかしながら,被相続人から生前贈与を受けるなどの利益を受けている相続人がいた場合,あるいは,被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人がいた場合にまで,相続開始時に存在した相続財産の総額を基準にして分配するだけでは,得をしたり,損をしたりする相続人が現れ,かえって不公平な相続となる場合があります。
そこで,被相続人から生前贈与を受けるなどの利益を受けている相続人がいた場合には「特別受益」,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人がいた場合には「寄与分」,という制度により,より公平な相続財産の分配を実現することができます。
今回のコラムでは,「特別受益」と「寄与分」に関して,ご説明いたします。
特別受益について
1 特別受益とは
特別受益(民法903条)とは,被相続人から生前贈与を受け,あるいは遺贈を受けた(遺言によって遺産を譲り受けた)相続人がいる場合,遺産分割の中で生前贈与や遺贈等の事情を考慮して,相続人間の公平を図ることを目的とするものです。
民法903条1項は,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな」すと規定し,利益を受けた者の受益額を遺産に持ち戻した上で,相続人それぞれの相続分を算定することになります。この利益を受けた額を相続財産に持ち戻した(加算した)金額を「みなし相続財産」といいます。
なお,公平の見地から,遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額と等しい若しくは超えているとき,受遺者又は受贈者は,相続分を受けることができなくなります(民法903条2項)。
2 特別受益の範囲
次に,特別受益に該当する対象について説明します。民法903条1項には,「遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」と規定されています。「生計の資本としての贈与」とは,生計の基礎として役立つような財産上の給付と考えられており,贈与の動機,遺産総額と贈与額の対比等の事情を総合的に考慮して,特別受益の該当性が判断されます。そのため,単なる生活費の援助,新築・入学の祝い金,結納金・挙式費用は,特別受益に該当しないと判断されることが多いです。
特別受益に該当する例としては,以下のものが挙げられます。
- 遺贈(遺言によって遺産を譲り受けること)
- 婚姻又は養子縁組のための贈与(持参金,支度金など)
- 大学の学費,留学費用など高等教育のための学資
- 事業を始めるための開業資金・住宅購入のための住宅資金・居住用の不動産の贈与
- 遺産不動産の無償使用
3 特別受益が認められる場合の具体的相続分の算定例
被相続人 X
相続人 妻A,子B・C
遺産評価額 3000万円
生前贈与 X → A 600万円
X → B 400万円
このような事例の場合,相続人それぞれの具体的相続分はいくらとなるのか,計算してみましょう。
【みなし相続財産】
3000万円 + 600万円 + 400万円 = 4000万円
【一応の相続分】(みなし相続財産に法定相続分を乗じた額)
妻A 4000万円 × 2分の1 = 2000万円
子B 4000万円 × 4分の1 = 1000万円
子C 4000万円 × 4分の1 = 1000万円
【具体的相続分】
妻A 2000万円 - 600万円 = 1400万円
子B 1000万円 - 400万円 = 600万円
子C 1000万円
「みなし相続財産」から,各人の一応の相続分を算出し,そこから生前贈与を受けた妻A及び子Cのみ,生前贈与を受けた金額を控除して具体的相続分を導くという計算を行うことで,生前贈与を受けた者と受けていない者の均衡が図れるのです。
寄与分について
1 寄与分とは
寄与分とは,被相続人の財産の維持又は増加に「特別の寄与」をした相続人がいたとき,その「特別の寄与」を考慮して,当該相続人に相続財産の中から寄与分額を加えた財産を取得させることをいいます(民法904条の2)。寄与分も,特別受益と同様に,共同相続人間の公平の見地から,具体的相続分の修正要素として用いられるものです。
2 寄与分の要件
寄与分を受ける者は相続人に限定されており,①「特別の寄与」であること,②相続人の寄与行為によって被相続人の財産が維持又は増加したこと,を満たす場合に認められる主張になります。
①「特別の寄与」とは,相続人が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えて,特別の貢献をしたことが求められます。例えば,夫婦間には協力扶助義務(民法752条)が,親族間には扶養義務(民法877条1項)が存在するため,これらの義務の範囲内の行為は特別の寄与にはならず,通常期待される程度を超えた寄与でなければなりません。
加えて,相続人の寄与行為によって,被相続人の財産・資産の維持又は増加,被相続人の消極財産(借金,地代・家賃等の支払債務)の減少又は消極財産増加の阻止等の事情が,②の要件として認められる必要があります。単なる精神的な支援だけでは認められません。
3 寄与行為の具体例
民法904条の2第1項は,寄与行為の例示として,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」と「被相続人の療養看護」を規定し,その他の方法によるものも認めています。寄与行為に該当する例としては,以下のものに分類できます。
①家事従事型
被相続人が営む事業に,無報酬,あるいは,ほとんど報酬を受けることなく,事業に従事し,被相続人の財産増加に貢献した場合に認められることがあります。
②療養看護型
特段の報酬を得ることなく,相続人が被相続人の療養看護に従事した場合,介護費用等の支出がなくなるため,相続財産の維持に貢献したとして認められることがあります。
③金銭等出資型
被相続人の営む事業への出資,被相続人所有の不動産への出資,施設入所費の支払いなど,被相続人に対する財産上の給付が寄与となる場合に認められることがあります。
④扶養型
要扶養状態にある被相続人に対し,報酬を受けることなく継続的に扶養した場合に認められるものですが,親族間には上記の扶養義務があるため,通常の扶養を超える支出が必要だと考えられています。例えば,病院への送迎のみであると,通常の扶養を超えるとはいえないおそれがあります。
⑤財産管理型
被相続人の財産管理に貢献し,管理費用の支払いが不要になった場合に認められることがあります。
4 特別受益が認められる場合の具体的相続分
被相続人 X
相続人 妻A,子B・C
遺産評価額 3000万円
寄与分 A 600万円 B 400万円
このような事例の場合,相続人それぞれの具体的相続分はいくらとなるのか,計算してみましょう。
【みなし相続財産】
3000万円 - 600万円 - 400万円 = 2000万円
【一応の相続分】(みなし相続財産に法定相続分を乗じた額)
妻A 2000万円 × 2分の1 = 1000万円
子B 2000万円 × 4分の1 = 500万円
子C 2000万円 × 4分の1 = 500万円
【具体的相続分】
妻A 1000万円 + 600万円 = 1600万円
子B 500万円 + 400万円 = 900万円
子C 500万円
「みなし相続財産」から,各人の一応の相続分を算出し,そこから特別の寄与があった妻A及び子Cのみ,寄与分額を加算して具体的相続分を導くという計算を行うことで,特別の寄与があった者となかった者の均衡が図れるのです。
5 令和元年7月1日施行の改正相続法による特別寄与制度の創設
令和元年7月1日に施行された改正相続法では,新たに特別の寄与の制度を創設し(民法1050条),相続人でなくても,被相続人の親族(民法725条)が,無償で被相続人の療養看護等の労務の提供をしたことによって,被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合には,相続人に対して特別寄与料の請求を行うことができることとなりました。
最後に
本コラムでは,相続発生時における特別受益と寄与分について解説いたしました。特別受益及び寄与分が認められるかについては,個別具体的事情をお伺いしないことには判断できず,専門的な知識を要する場面が多々ございます。
相続開始時に現存していた相続財産を法定相続分に従って分配するだけでは納得できない時,被相続人の親族が被相続人の財産の維持又は増加に貢献していたことを加味して欲しい時,その他相続に関するご質問がございましたらお気軽にご相談ください。